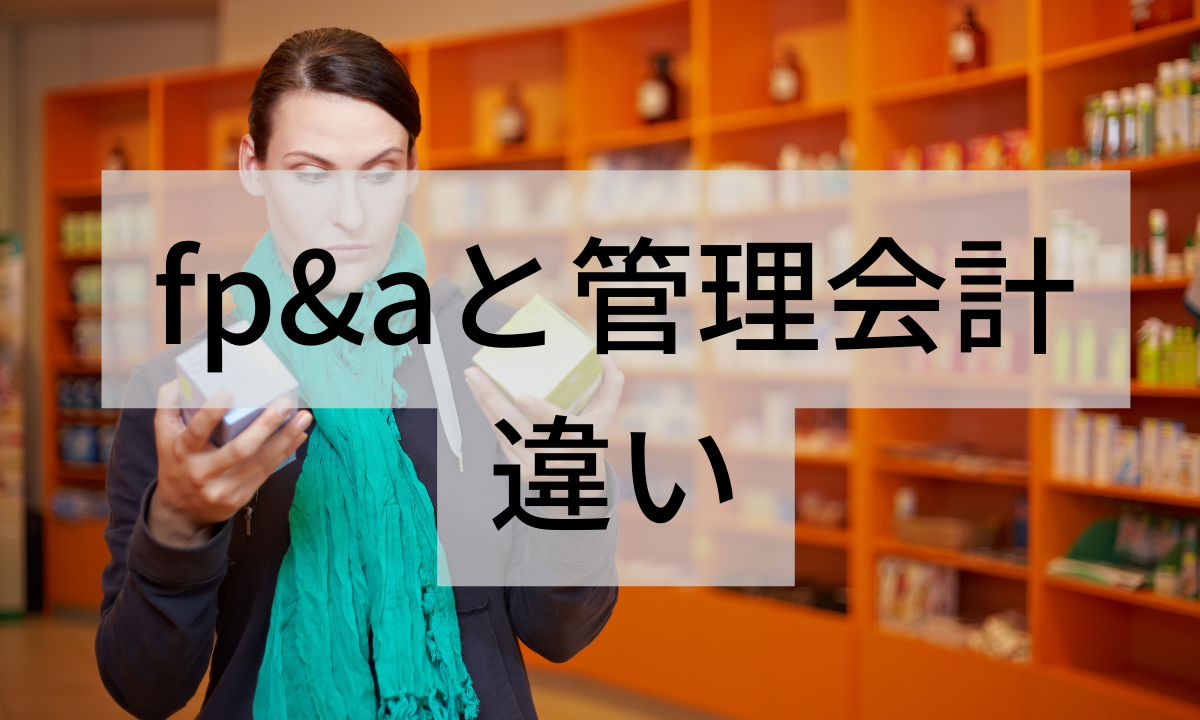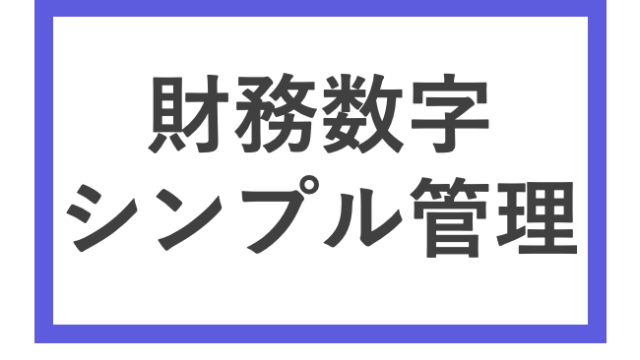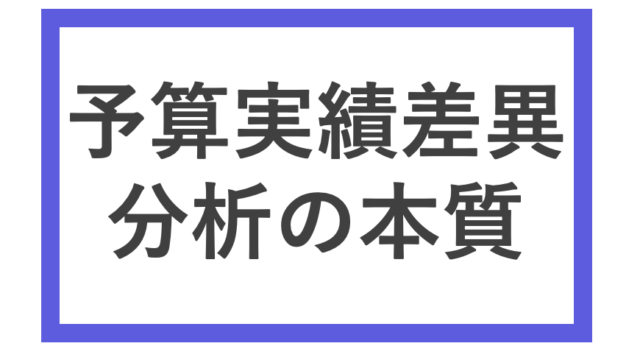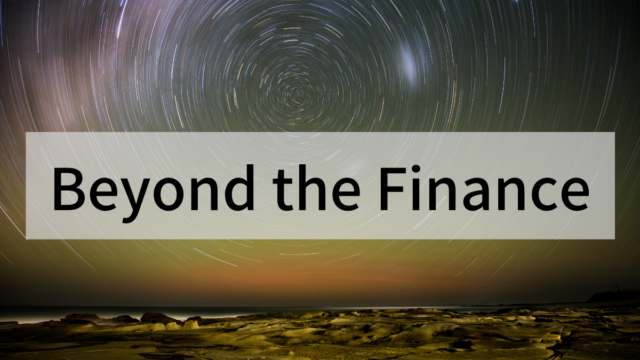こんにちはゲンタです。
今日はfp&aと管理会計の違いを説明します。
fp&aは元々外資系の会社から始まった概念です。
一方で管理会計は日系の経営企画部などで行われている概念です。
最近では日系企業でもfp&aと言う役職を設置する流れが始まっています。
例えば、NEC、リクルート、ソフトバンク、資生堂などです。
この傾向は今後も強まっていくことは間違いなく
外資系のfp&aという機能の実態を理解しておくことは
我々、経理マンとしては必須です。
旧来型の管理会計と現在のfp&aは一体何が違うのでしょうか?
ここをしっかりと説明していきます。
(結論)fp&aと管理会計の違い
ごちゃごちゃ言わずにまずは結論から行きます。
fp&aと管理会計の違いポイント
・日系企業の管理会計は集計機能がメインであり外資系のfp&aは意思決定機能がメインであり、実際に果たせる役割が異なる。
・果たせる役割の違いが発生する要因は組織構成と人員体制である。組織構成と人員体制が異なるため、果たせる機能が大きく違ってくる。
・本来の管理会計の役割には意思決定機能も含まれるが、事実上その機能は発揮できておらず、ある意味で本来の管理会計の意義を形にしたのがfp&aだとも言える。
fp&aと管理会計の比較表
fp&aと管理会計の主要な違いを項目ごとにチャートにしました。
これを見れば組織構成の違いによって
発揮する機能の違いが出てくることがわかります。
特に赤字の箇所がポイントです。
| 項目 | fp&a | 管理会計 |
|---|---|---|
| 企業形態 | 外資系企業 | 日系企業 |
| 所属部署 | ファイナンス部 or 各事業部門(工場、物流、開発、人事、マーケティング等含む) |
経営企画部 |
| レポートライン | ①CFO ②事業部門責任者 |
経営企画部責任者 |
| 重要なスキル | ・コミュニケーション力 (ある意味で腕力、決定力) ・ファイナンスの専門知識 |
・コミュニケーション力 ・エクセル集計スキル |
| 求められる機能 | ・中期計画の策定 ・事業計画の策定 ・フォーキャストと実績のトラック ・商品別チャネル別PLのトラック ・KPIの設定とトラック ・課題発見と課題解決策の提案 ・リスクとオポチュニティの発見 ・事業部門長に対する意思決定判断サポート ・CFOに対するレポート |
・中期計画の策定 |
| 実態としての機能 | ・事業部門付きのfp&aによって、各部門の経費管理からプライシング、設備投資、開発投資、新製品施策などの意思決定サポートが行われる。 ・CFOがドットラインのあるfp&aからのレポートで社内のあらゆる機能における金の流れを詳細に把握することができる。 |
・全社の事業計画や見込みの集計係となっているケースが多い。 ・各部門でどのような事業を行っているのか見えにくく実態を把握しきれない。 ・実績データは経理部が握っていて把握がしきれない。 |
| 大きな違い | 部門付きfp&aも入れるとファイナンス人員数が多い 毛細血管のように社内のあらゆる数字を拾い集める仕組みとなっている |
ファイナンス人員は本社機能に留まり、事業部門にファイナンス人員を送った場合はCFOにドットラインはなく、レポートされることはない。そのため、CFOは会社全体の数字が漠然とはわかるが、詳細に把握することが難しい |
日系企業の管理会計業務の実態
次に日系企業の管理会計業務の実態を説明します。
日系企業で行われている管理会計業務は実態的には
経営企画部で行われる様々な業務の中の一つとして
片手間的に行われています。
経営企画部は他にもたくさんの業務を行っています。
会社規模によって業務範囲は異なりますが
下記のような業務が一般的には業務範囲となります。
<経営企画部の業務>
- 経営戦略の策定
- 中期計画の策定
- 事業計画の策定
- 見込み、業績管理
- M&A
- 組織再編
- グループ会社管理
- IR
- コーポレートガバナンス
- 渉外
- 経営者からのアドホック業務
経営企画部が担当する管理会計の業務というのは
この中の事業計画の策定や見込みと業績管理になります。
実態としてそりゃあ
各事業の細かな数字を追いかけるなんてことは
片手間でできるわけありません。
全社的な数字の取りまとめをして終わって当然です。
事業部の実態を知るためには各部に
ヒアリングしなければならないわけです。
つまり各事業部門でどれだけ精緻に数値管理を行っているのかが
日系企業の管理会計のレベルを分けます。
中には商品ごとやチャネルごとのPL管理を行っている会社もありますが
ごくごく少数でほとんどの会社ではそういった管理ができていないようです。
それが日系企業の管理会計の実態です。
(考察)日系の管理会計の課題と対処策
先ほどのチャートがほぼすべてを表していますが
日系の管理会計の問題点を浮き彫りにしています。
結局、人の力と権力の置き方に課題があるということです。
各事業部門にもCFOにドットラインのある
ファイナンススタッフをfp&aとして配置し
数値管理を徹底するのが外資系です。
日系では各事業部門にファイナンススタッフをおくことはなく
ドットラインもないため事業部門の実態をCFOが知る術が
限定的で数値管理の徹底がしにくいというわけです。
日系企業ではそこまで大胆にCFOの権力を置いておらず
外資系企業ではより明確にCFOの権力を発揮できる
組織形態になっているというわけです。
その結果、日系の管理会計機能は弱く
全社的な集計作業に終始してしまっている。
本来の管理会計の役割である
経営者の意思決定サポートという機能を発揮できていない状況が
できてしまっている。
日系企業がfp&a機能を配置するための解決策
結局は社長の考え方を変えなければなりません。
社長がCFOの権力を高めていき
数字でしっかりと経営をハンドルしたいと
思わせなければ実現しません。
その施策として費用をかけてでも
ファイナンススタッフを増強するなり
各事業部門にいる数値管理スタッフを再教育して
fp&aとしてCFOにドットラインのあるファイナンススタッフを
各部門に配置して数値管理を徹底する。
全体のコストを変えずに人員の再教育というのは
ある意味で現実的なシナリオだと思います。
(備考)外資系組織におけるCFOの力が強まった経緯
なぜ外資系ではこのようにCFOに強大な権力を集中させる形態を取ったのでしょうか?
答えはもちろんその方が会社の企業価値が高まるからです。
外資系のfp&aがこのような組織形態になった経緯は
ITTの社長だったハロルドジェニーンにあると言われています。
ハロルドジェニーンという人はコングロマリット企業ITTの社長でしたが
元々は公認会計士であり、その後は経理部長などを経て社長になった人です。
ハロルドジェニーンは現場の仕事をファイナンス面で分析して業績を上げていきました。
この手法を使ってITTでも詳細に直接トップにレポートさせる体制を構築したわけです。
そしてこれが他の企業にも広がっていったと言われています。
ハロルドジェニーンの著書はユニクロの柳井正さんや
CFOで有名な石橋善一郎さんも推薦されていて一度読んでみるといいと思います。
fp&aと管理会計の違いのまとめ
今日の話をまとめます。
・日系企業の管理会計は集計機能がメインであり外資系のfp&aは意思決定機能がメインであり実際に果たせる役割が異なる。
・果たせる役割の違いが発生する要因は組織構成と人員体制である。組織構成と人員体制が異なるため果たせる機能が大きく違ってくる。
・本来の管理会計の役割には意思決定機能も含まれるが、事実上その機能は発揮できておらず、ある意味で本来の管理会計を形にしたのがfp&aだとも言える。
上記外資との違いから考察できる日系企業の管理会計の課題を下記にまとめます。
<日系企業の管理会計の課題>
各事業部門にファイナンススタッフを設置されておらず
CFOにドットラインもないため事業部門の実態をCFOが知る術が限定的で
各事業部門の数値管理の徹底がしにくい
これを踏まえて具体的に日系企業がfp&aとして
本来の管理会計の役割を果たすための解決策は次のようになります。
<日系企業の管理会計をfp&aにグレードアップさせる解決策>
費用をかけてでもファイナンススタッフを増強するか
各事業部門にいる数値管理スタッフを再教育して
fp&aとしてCFOにドットラインのあるファイナンススタッフを
各部門に配置して数値管理を徹底する。
全体のコストを変えずに人員の再教育というのは
ある意味で現実的なシナリオである
ということで、
本日は管理会計とfp&aの違いの解説と
日系企業の管理会計の強化策の話でした。
ゲンタ
こんにちはゲンタといいます。
自己紹介をします。
<昔>
・元ニート兼プータロー
・零細企業経理部で伝票を起票したり請求書を発行したりと作業仕事
・年収は300万円で、超いけてない経理マン
↓その後、改善施策を実施
<今>
・海外CFO
・従業員数千人企業の管理部門、M&A、FP&Aを統括
・年収は数千万
大きく変わることができました。
変わるポイントは作業型から思考型に仕事を変えていったことでした。
ブログのコンセプトは、 Beyond the Financeと言います。
なんだそりゃって感じですよね?
”作業地獄型の経理から脱出して、思考型経理になろう”
というのがその意味です。
思考型経理って一体なんだろう?と思っていただけたら
下記のリンクから読み進めていってください。
皆さんの人生が変わるきっかけになるかもしれません。
よろしくお願いします。
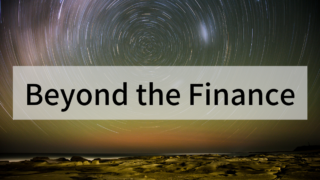
ゲンタ