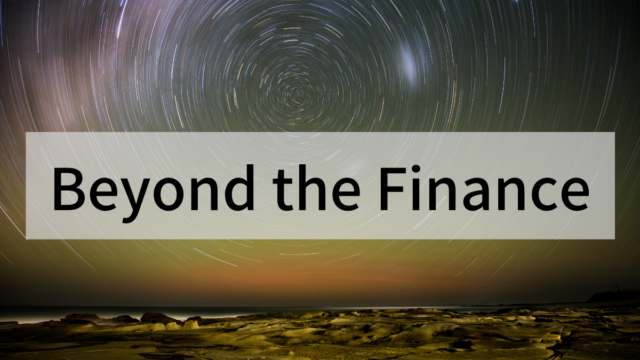こんばんはゲンタです。
今日は引き続き経理マンに取ってマストで知っておくべき
ERPについての続きです。
DXが流行っている中で、
ERPはどう位置付けられていくのか?
という話をします。
ずばり、ERPは引き続き
企業の基幹業務を担うコアシステムとして
重要性がさらに増していきます。
なのでERPの今後の方向性について理解していれば、
業務を行うときに
どのようにERPに接していけば良いかわかるので非常に有利です。
ERPの今後の位置付け2点
今後のERPの位置付けのポイントとしては2点あります。
1 周辺システム、エクセルファイルとの連携効率化、自動化を推進
2 マーケティング、crmなどとの連携強化による意思決定のAI化、ビッグデータの活用
この2つです。
1点目は理解しやすいと思います。
要はERPは基幹業務であるためERP外で行う業務においても
自動化をRPAなどで行うことによって、
基幹業務プロセスの効率化=コスト削減を行う
というものですね。
ホワイトカラーの業務も工場のように工程を効率化していくべきという方向の一環です。
銀行の業務もどんどん自動化が進んでますが、
ああいった流れと同様です。
その中にERPがあるというイメージです。
2点目は少し理解しにくいかもしれません。
これはこれまでソフトなデータとして扱われてきた
マーケティング関連のデータであるマーケットのデータ(シェア、競合の商品の売れ行き、ユーザーの反応)、営業部が抱えるお客さん関連の細々としたデータの蓄積
といったデータ
こういったカチッとしたデータではないものと
ERPに入っている過去のカチッとしたデータを組み合わせて
AIで意思決定を自動的に生み出す。
という使い方です。
ERPに蓄積されたデータをその他のソフトデータと組み合わせて
ビッグデータとして扱うという考え方です。
例えば、これによって不正の予知などもチェックすることができたりするはずです。
こういった使い方が大きく2点ERPの周辺で発生していく方向性だと考えられます。
じゃあ、僕ら経理マンはどうすればいいの?
だからこそ経理マンは基礎としてERPを確実に理解しなければならない。
でもERPでさえきちんと全体像を理解してる人は非常に少ないです。
なぜなら、経理の自分の部署と関係ないところで、
他部署で基幹業務を行って入力すると自動的に仕訳がきられてしまい、
どのようなフローでGLにきているのかわかりにくいからです。
また自動仕訳できられる仕訳の量はボリュームが多いのと
仕訳も一般的に手できる仕訳と異なっていて
いったいどんなロジックで数字が計算されているのかパッとわかりにくいです。
この基幹業務のフローと自動仕訳のロジックをきちんと理解しなければ、
ERPを本当に理解したとはいえません。
逆にこれがわかってる人はライバルに先行できます。
DXへの対応も強くなれます。
ということでERPの基礎をきちんと理解した上で
今後の方向性をわかっている人は希少性が高いのでお得です。
という話でした。
ゲンタ
こんにちはゲンタといいます。
自己紹介をします。
<昔>
・元ニート兼プータロー
・零細企業経理部で伝票を起票したり請求書を発行したりと作業仕事
・年収は300万円で、超いけてない経理マン
↓その後、改善施策を実施
<今>
・海外CFO
・従業員数千人企業の管理部門、M&A、FP&Aを統括
・年収は数千万
大きく変わることができました。
変わるポイントは作業型から思考型に仕事を変えていったことでした。
ブログのコンセプトは、 Beyond the Financeと言います。
なんだそりゃって感じですよね?
”作業地獄型の経理から脱出して、思考型経理になろう”
というのがその意味です。
思考型経理って一体なんだろう?と思っていただけたら
下記のリンクから読み進めていってください。
皆さんの人生が変わるきっかけになるかもしれません。
よろしくお願いします。
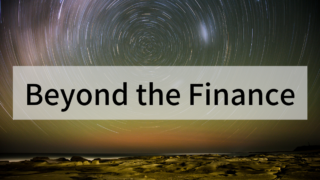
ゲンタ